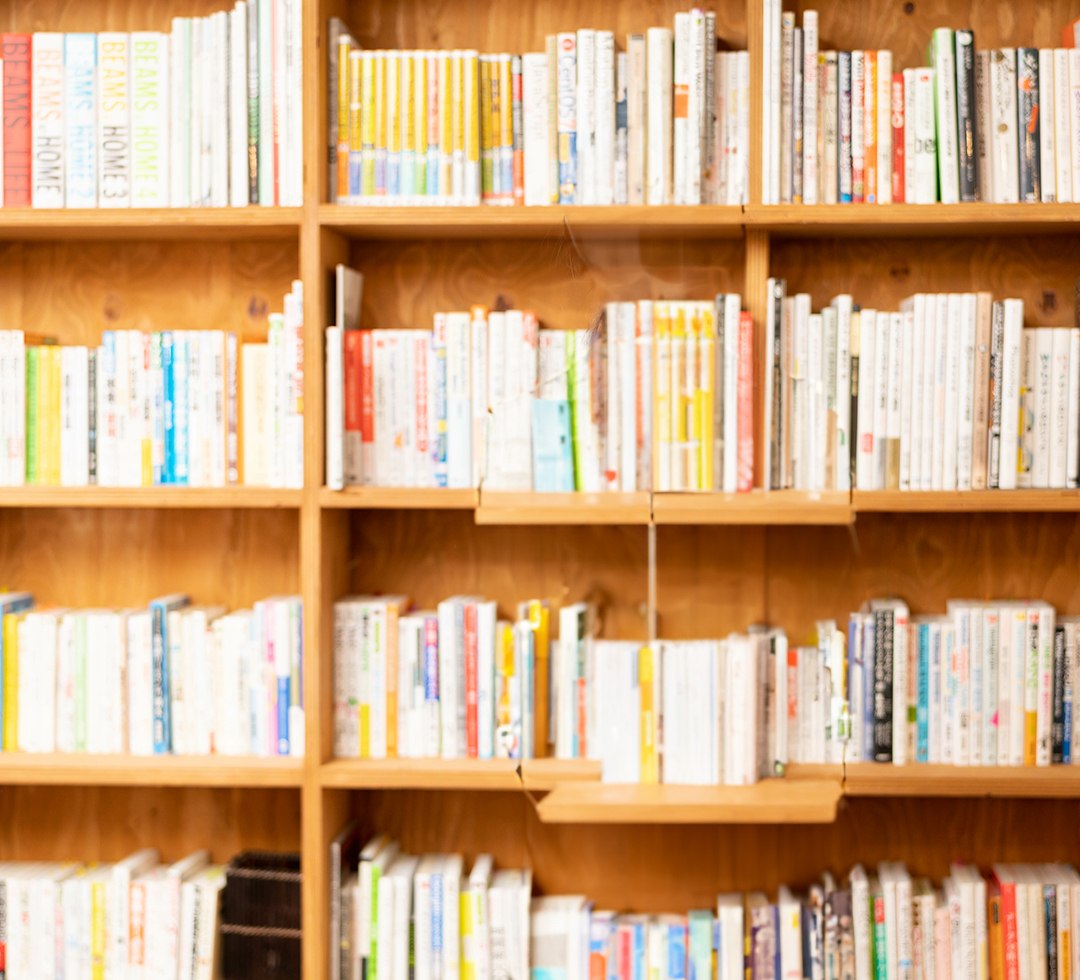オフィシャルブログ
二次相続とは?
一次相続より負担が重くなる理由と
効果的な対策

相続には「一次相続」と「二次相続」があります。
- 一次相続:親の片方が亡くなり、配偶者と子どもが相続する
- 二次相続:残された配偶者が亡くなり、子どもが相続する
一次相続と二次相続では、相続税の負担や対策方法が異なります。特に二次相続では配偶者控除が使えなくなるため、相続税が重くなりがちです。
本記事では、二次相続で発生する問題と効果的な対策法を詳しく解説します。
1. 二次相続で税負担が増える理由
① 配偶者控除が使えない
最も大きな理由がこのためです。一次相続では、残された配偶者が法定相続分(または1億6,000万円)のどちらか多い金額までは、相続税がかからない「配偶者控除」が適用されます。
そのため、一次相続では配偶者に多くの財産を相続させることで相続税を抑えるケースが多いです。
しかし、二次相続では配偶者控除が使えないため、子どもがすべてを相続し、相続税の負担が一気に増加します。
② 基礎控除額が減少
相続税には基礎控除額が設けられており、
3,000万円+600万円×法定相続人の数 が控除されます。
一次相続では配偶者が相続人に含まれるため控除額が大きくなりますが、二次相続では子どもだけが相続人になるため基礎控除が減少します。
③ 相続税率の累進課税による負担増
相続税は累進課税方式のため、課税対象額が増えると税率も上がります。
一次相続で配偶者に大部分を相続させると、二次相続時に課税遺産総額が大きくなり、高税率が適用されやすくなります。
2. 二次相続での主な対策法
① 一次相続で配偶者に偏らせすぎない分割
一次相続では配偶者控除を利用して税負担を抑えられるため、配偶者に遺産を多く相続させるケースが一般的です。しかし、この方法は二次相続での税負担を重くする原因となります。
そこで、一次相続時に配偶者だけでなく子どもにも一定の財産を分け与えることで、二次相続時の課税対象額を減らす工夫が重要です。
具体例:遺産1億円の場合の分割シミュレーション
相続人が配偶者と子ども2人の場合の基礎控除額
- 一次相続:3,000万円+600万円×3=4,800万円
- 二次相続:3,000万円+600万円×2=4,200万円
【ケース1】
一次相続で配偶者が全額相続し、二次相続で子が相続する場合
- 一次相続時の課税遺産額:1億円
- 配偶者控除1億6,000万円の適用 → 相続税は0円
- 二次相続時の課税遺産総額:1億円
- 基礎控除:4,200万円
- 課税対象額:1億円-4,200万円=5,800万円
- 税額計算:
5,800万円×15%-50万円=820万円 - 合計税額:約820万円
【ケース2】
一次相続で配偶者が6,000万円、子どもが4,000万円を相続する場合
- 一次相続時の課税遺産額:1億円
- 配偶者:6,000万円 → 配偶者控除1億6,000万円適用 → 税額0円
- 子ども:4,000万円 → 基礎控除4,800万円以内 → 税額0円
- 二次相続時の課税遺産総額:6,000万円
- 基礎控除:4,200万円
- 課税対象額:6,000万円-4,200万円=1,800万円
- 税額計算:
1,800万円×10%=180万円 - 合計税額:180万円
結果:合計税額が約640万円軽減
一次相続で子どもにも分けることで、二次相続時の課税対象を圧縮でき、税負担が大幅に軽くなります。
② 生命保険を活用して現金を確保
生命保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税になります。
二次相続では税負担が増えるため、一次相続時に生命保険を活用し、子どもが納税資金を確保できるようにしておくと安心です。
③ 生前贈与で資産を移転する
二次相続に備え、生前に子どもへ贈与するのも有効な対策です。
暦年贈与では、年間110万円まで非課税で贈与できます。
また、2024年からは「相続時精算課税制度」の基礎控除が110万円に拡大され、使いやすくなっています。
また、二次相続で遺産分割協議を行うことになった場合、親族間で揉める可能性があります。
そこで、一次相続時に遺言書を作成し、二次相続時の分割方法を指定しておくことで、トラブルを防ぎつつ節税対策ができます。
3. まとめ
二次相続は一次相続よりも税負担が増える傾向があるため、一次相続時から対策が必要です。
- 一次相続で配偶者に偏りすぎない分割
- 生命保険で納税資金を確保
- 生前贈与で課税対象を圧縮
- 遺言書で分割方針を明確に
これらの対策を行うことで、二次相続時の負担を軽減できます。
相続は早めの対策が重要ですので、お早めにご検討ください。