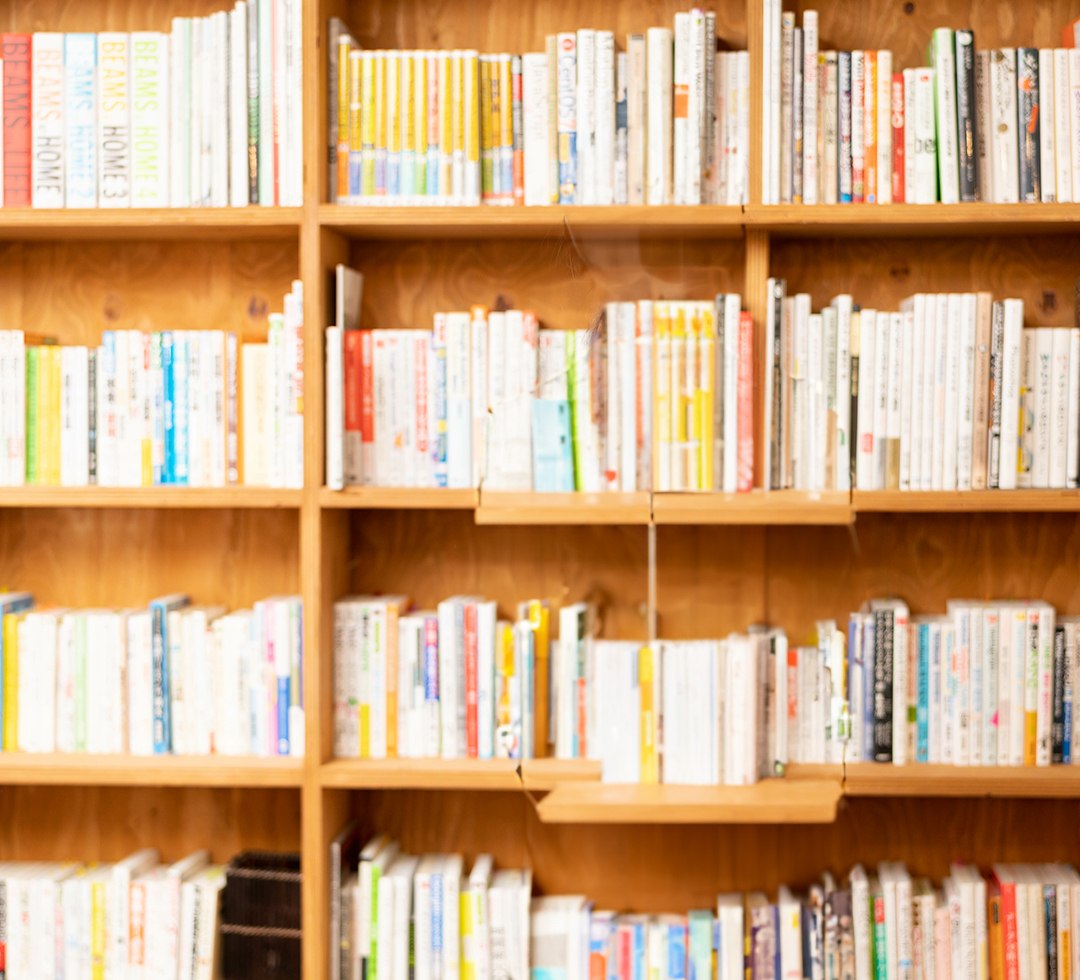オフィシャルブログ
相続時の「小規模宅地等の特例」とは?

相続税は不動産の評価額に基づいて課税されるため、不動産を多く保有している場合には高額な相続税が発生します。しかし、相続時には「小規模宅地等の特例」を適用することで、最大80%もの減額が可能です。
この特例を活用すれば、相続税負担を大幅に軽減できるため、不動産を相続する方にとっては必須の制度といえます。
本記事では、小規模宅地等の特例の内容や要件、注意点をわかりやすく解説します。
1. 小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた宅地について、一定の要件を満たす場合に評価額を減額できる制度です。
この特例が適用されることで、相続税評価額が最大で80%減額されます。
【減額割合と対象面積】
| 種類 | 減額割合 | 対象面積の上限 |
|---|---|---|
| 居住用宅地 | 80%減額 | 330㎡まで |
| 事業用宅地 | 80%減額 | 400㎡まで |
| 貸付事業用宅地 | 50%減額 | 200㎡まで |
2. 適用要件
① 居住用宅地の要件
被相続人が自宅として住んでいた宅地を**配偶者、同居親族、別居親族(家を所有していない)**が相続した場合に適用されます。
【適用条件】
- 配偶者が相続 → 無条件で適用可能
- 同居親族が相続 → 相続後も引き続き居住する必要あり
- 別居親族が相続 → 相続人に持ち家がなく、相続税申告期限まで所有・利用する必要あり
ポイント
配偶者が相続する場合は要件が緩いため、特例が受けやすいです。一方で、別居親族の場合は自宅を持っていると適用されないので注意が必要です。
② 事業用宅地の要件
被相続人が事業を営んでいた宅地を事業承継した相続人が相続した場合に適用されます。
【適用条件】
- 被相続人が事業を営んでいた土地であること
- 相続人が引き続き事業を継続すること
- 相続税申告期限まで事業を続けていること
ポイント
事業を継続することが前提のため、廃業すると特例は受けられません。
③ 貸付事業用宅地の要件
被相続人が貸付事業(アパート経営など)で使用していた土地を相続した場合に適用されます。
【適用条件】
- 被相続人が生前に貸付事業を営んでいたこと
- 相続人が引き続き貸付事業を継続すること
- 相続税申告期限まで貸付を続けること
ポイント
貸付事業用宅地は減額割合が50%と他より低く、対象面積も200㎡までと限られています。
3. 節税効果のシミュレーション
実際に小規模宅地等の特例を適用した場合と適用しない場合で、相続税がどの程度変わるのかをシミュレーションします。
〈ケース〉
- 被相続人:父親
- 相続人:子ども1人
- 自宅宅地の評価額:5,000万円
- 基礎控除:4,200万円(3,000万円+600万円×2人)
【特例を適用しない場合】
- 課税価格:5,000万円-4,200万円=800万円
- 相続税額:
800万円 × 15% - 50万円=70万円
【特例を適用した場合】
- 自宅宅地評価額:5,000万円×20%=1,000万円に減額
- 課税価格:1,000万円-4,200万円=非課税
結果:相続税が0円に!
特例を適用することで相続税負担が大幅に軽減されます。
4. 小規模宅地等の特例の注意点
① 申告期限までの継続利用が必須
特例を適用するためには、相続税の申告期限(被相続人の死亡から10カ月以内)まで宅地を継続して使用する必要があります。
途中で売却したり賃貸に出したりすると、特例が無効になるので注意しましょう。
② 共有名義で相続すると適用範囲が制限される
共有で宅地を相続した場合、特例の対象面積は持分に応じて按分されます。
例)400㎡の宅地を2人で相続(50%ずつ) → 特例の対象面積はそれぞれ200㎡まで
③ 貸付事業用宅地は要注意
貸付事業用宅地は減額割合が50%に留まり、要件も厳しくなっています。
例えば、アパート経営をしていた場合、被相続人が生前に事業として行っていた実態がなければ適用されません。
5. まとめ
小規模宅地等の特例は相続税対策として非常に有効な制度です。
- 居住用宅地は最大80%減額
- 事業用宅地は最大80%減額
- 貸付事業用宅地は最大50%減額
この特例を活用することで、不動産の相続税負担を大幅に軽減できます。
しかし、要件を満たさないと適用されないため、早めに対策を検討することが重要です。