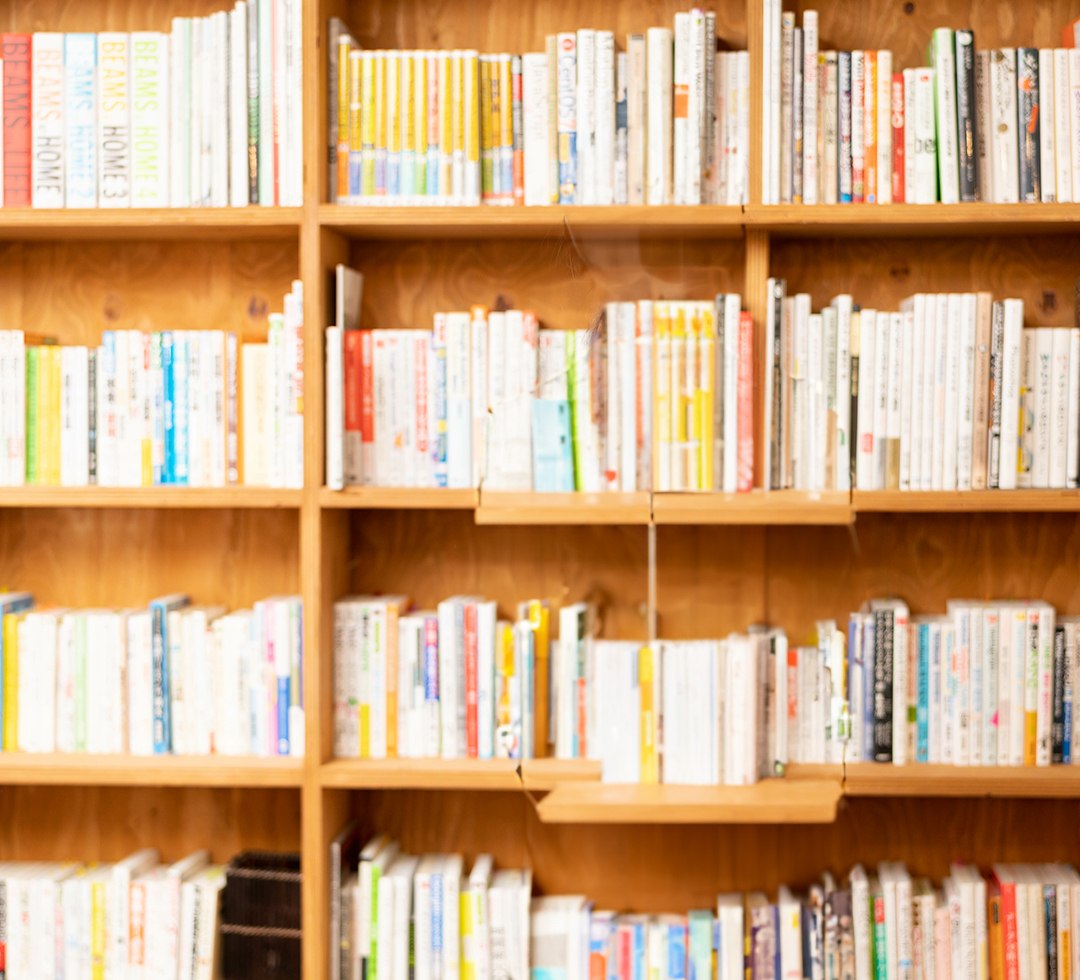オフィシャルブログ
相続手続きチェックリスト

被相続人が亡くなった後の相続手続きは、さまざまな期限が設定されており、期限を守ることが重要です。以下に死亡後の相続手続きを、期限ごとに整理しましたので、参考にしてください。
1. 死亡後7日以内にやるべき手続き
(1) 死亡届の提出
- 提出先:故人の住民票があった市区町村役場
- 提出期限:死亡後7日以内
- 必要書類:死亡届・死亡診断書
- 死亡届を役所に提出します。A3用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書になっています。この書類は各種手続きに必要です。原本を役所に提出してしまう前に、必ず多めにコピーを取っておきましょう。
(2) 火葬許可申請
- 提出先:市区町村役場
- 提出期限:死亡後7日以内
- 必要書類:死亡診断書
- 火葬を行うために必要な許可を申請します。葬儀会社が代行して出してくれる場合が多いです。
2. 死亡後10日以内にやるべき手続き
厚生年金保険証の返納
- 提出先:市区町村役場
- 提出期限:死亡後10日以内
- 必要書類:健康保険証
- 健康保険証を返納し、医療費の請求を停止します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、役所に死亡届を提出することによって、その情報が年金事務所にも共有されるため、手続は不要です。日本年金機構に故人のマイナンバーが収録されているかどうかを知るには、年金事務所に確認をする必要があります。
3. 死亡後14日以内にやるべき手続き
(1) 世帯主変更届
- 提出先:市区町村役場
- 提出期限:死亡後14日以内
- 必要書類:死亡届受理証明書
- 故人の世帯主変更手続きを行います。
(2) 児童扶養手当認定請求
- 提出先:市区町村役場
- 提出期限:死亡後14日以内
- 必要書類:死亡証明書、戸籍謄本
- 未成年の子どもがいる場合、手当の認定手続きを行います。
(3) 国民健康保険証の返納
- 提出先:市区町村役場
- 提出期限:死亡後14日以内
- 必要書類:健康保険証
- 健康保険証を返納し、医療費の請求を停止します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、役所に死亡届を提出することによって、その情報が年金事務所にも共有されるため、手続は不要です。日本年金機構に故人のマイナンバーが収録されているかどうかを知るには、年金事務所に確認をする必要があります。
(4) 介護保険資格喪失届
- 提出先: 市区町村の役所
- 必要書類: 死亡証明書、介護保険証
- 概略: 故人が介護保険を受けていた場合、その資格を喪失するための手続きを行います。これにより介護保険の適用が終了し、今後の支払いが停止します。
(5) 後期高齢者医療障害認定資格喪失届
- 提出先: 市区町村の役所
- 必要書類: 死亡証明書、後期高齢者医療証
- 概略: 後期高齢者医療制度に加入していた場合、その資格を喪失するための手続きを行います。これにより、医療費助成が停止します。
(6) 特定疾患医療受給者の手続き
- 提出先: 市区町村の役所
- 必要書類: 死亡証明書、特定疾患受給者証
- 概略: 特定疾患に関する医療受給者証を持っている場合、その資格喪失手続きが必要です。医療助成の資格が終了しますので、適切な手続きを行いましょう。
(7) 身体障害受給者の手続き
- 提出先: 市区町村の役所
- 必要書類: 死亡証明書、身体障害者手帳
- 概略: 故人が身体障害者手帳を持っていた場合、資格喪失の手続きを行います。これにより、障害者手帳に基づく各種支援が停止します。
4. 死亡後3ヶ月以内にやるべき手続き
(1) 相続放棄または相続承認の選択
- 提出先:家庭裁判所
- 提出期限:死亡後3ヶ月以内
- 必要書類:戸籍謄本、相続放棄申述書
- 相続人が相続放棄または承認を選択する場合の手続きです。
5. 死亡後4ヶ月以内にやるべき手続き
(1) 準確定申告
- 提出先:税務署
- 提出期限:死亡後4ヶ月以内
- 必要書類:確定申告書、死亡診断書、収入証明書
- 故人の収入に関する確定申告を行います。
6. 死亡後10ヶ月以内にやるべき手続き
(1) 遺産分割協議書作成
- 提出先: 相続人全員(協議を行う)
- 必要書類: 相続人全員の署名・捺印がされた遺産分割協議書
- 概略: 相続人全員が集まり、相続財産の分割方法について協議します。合意が得られたら遺産分割協議書を作成し、署名・捺印を行います。
(2) 相続税の申告・納付
- 提出先:税務署
- 提出期限:死亡後10ヶ月以内
- 必要書類:相続税申告書、遺産分割協議書
- 相続税が発生する場合、申告と納付を行います。
7. すみやかにやるべき手続き
(1) 死亡退職届の手続き
- 提出先:故人が勤務していた会社
- 必要書類:死亡証明書、退職届
- 退職手続きを行い、退職金の支払いを受けます。勤務先も亡くなった日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する必要があるため、亡くなったらすぐに連絡しましょう。
(2) 自筆証書遺言の検認
- 提出先: 家庭裁判所
- 必要書類: 自筆証書遺言
- 概略: 故人が自筆証書遺言を残している場合、その遺言の検認手続きが必要です。遺言が正当であることを確認するため、家庭裁判所に申立てを行います。
(3) 電気・ガス・水道の名義変更
- 提出先:電力会社、ガス会社、水道局
- 必要書類:死亡証明書、相続人の確認書類
- 電気、ガス、水道の名義変更手続きを行います。
(4) 電話の名義変更
- 提出先:NTT
- 必要書類:死亡証明書、契約者情報
- 故人名義の電話契約を名義変更します。
(5) 携帯電話の解約
- 提出先:携帯電話会社
- 必要書類:死亡証明書、契約者情報
- 携帯電話の契約を解約または名義変更します。
(6) クレジットカードの解約
- 提出先:クレジットカード会社
- 必要書類:死亡証明書、カード
- 故人のクレジットカードを解約します。
(7) NHK受信料の名義変更
- 提出先:NHK
- 必要書類:死亡証明書
- NHKの受信契約を名義変更します。
(8) プロバイダーの名義変更
- 提出先:インターネットプロバイダー
- 必要書類:死亡証明書
- インターネット契約を名義変更します。
(9)賃貸住宅の名義変更
- 提出先:不動産会社
- 必要書類:死亡証明書、賃貸契約書
- 故人名義の賃貸契約を名義変更します。
(10)住宅火災保険の名義変更
- 提出先:保険会社
- 必要書類:死亡証明書、契約内容
- 住宅火災保険の名義変更手続きを行います。
(11) 借金(住宅ローン・クレジットなど)の名義変更
- 提出先:借入先
- 必要書類:死亡証明書、借入契約書
- 住宅ローンやクレジットカードなど、借金の名義変更を行います。
(12) 生命保険契約
- 提出先: 生命保険会社
- 必要書類: 死亡証明書、保険証券、保険金請求書、相続人の確認書類
- 概略: 故人が加入していた生命保険契約の名義変更または保険金の請求手続きを行います。相続人が契約を引き継ぐ場合や、保険金を受け取る場合の手続きです。
8. 遺産分割協議が整ったら行う手続き
(1)不動産の名義変更
- 提出先: 法務局
- 必要書類: 死亡証明書、戸籍謄本、相続人全員の同意書(遺産分割協議書)、不動産登記簿謄本
- 概略: 故人の所有する不動産の名義変更を行います。相続人が新たな所有者として登記されることで、不動産の権利が移転します。相続により所有権の取得を知った日から3年以内に行う必要があります。
(2) 自動車の名義変更
- 提出先: 陸運局(運輸支局)
- 必要書類: 死亡証明書、車検証、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、車両所有者の印鑑
- 概略: 故人の所有する自動車の名義を相続人に変更します。遺産分割協議に基づき、車両の所有権が移転されます。
(3) 預貯金の名義変更
- 提出先: 銀行
- 必要書類: 死亡証明書、通帳、印鑑証明書、遺産分割協議書(必要に応じて)
- 概略: 故人名義の口座の名義を相続人に変更します。銀行に必要書類を提出し、口座名義の変更手続きを行います。
(4) 株式の名義変更
- 提出先: 証券会社
- 必要書類: 死亡証明書、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書、証券口座の契約書
- 概略: 故人が所有していた株式の名義変更手続きを行います。証券会社に必要書類を提出し、株式を相続人の名義に変更します。
9. まとめ
相続手続きにはさまざまな期限が設けられています。法的に決められた期限を守り、遅れないように手続きを進めることが大切です。遺産分割協議、相続税申告、名義変更など、多くの手続きが必要となりますので、早めに取り組むことが重要です。