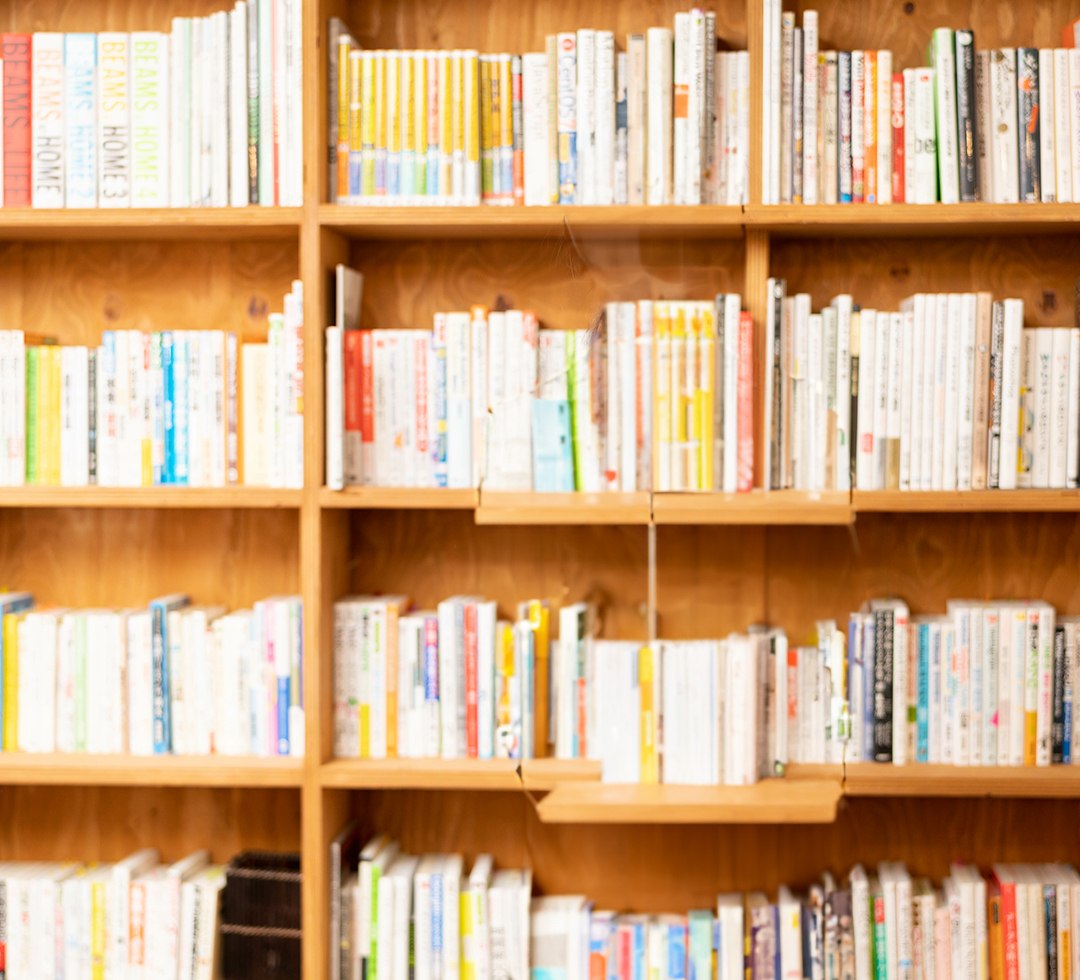オフィシャルブログ
亡くなった人に借金が?
相続前に知っておきたい調べ方と対処法を解説

親や親族が亡くなった後に財産を相続する際、思わぬ「負の遺産」として借金が発覚するケースがあります。
例えば、以下のような状況で借金が見つかることがあります。
-
銀行や消費者金融からの督促状が届いた
-
クレジットカードの未払い明細が見つかった
-
不動産に抵当権が設定されていた
-
故人が連帯保証人になっていた
相続では故人のプラスの財産(現金・不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金・未払金)も引き継ぐことになります。そのため、相続前にしっかりと借金の有無を調べ、適切な対処をすることが重要です。
1.故人の借金を調べる方法
故人の借入状況を調べるには、以下の手段があります。
(1)郵便物や書類を確認する
故人宛てに届く郵便物から借入先や返済状況が分かる場合があります。
-
銀行やローン会社からの督促状
-
クレジットカードの請求明細
-
債権回収会社からの通知書
(2)信用情報を開示する
信用情報機関に開示請求を行うと、故人の借入状況が分かります。主な機関は以下の3つです。
-
CIC(指定信用情報機関):クレジットカード・消費者金融の情報
-
JICC(日本信用情報機構):消費者金融・信販会社の情報
-
KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行や信用金庫の情報
開示請求の方法
-
必要書類:故人の戸籍謄本・死亡診断書・相続人の本人確認書類など
-
手数料:1回あたり1,000円前後
(3)法務局で登記情報を確認する
不動産を相続する場合は、法務局で登記簿謄本を取得し、抵当権や根抵当権が設定されていないか確認しましょう。これにより、故人が借金の担保として不動産を差し出していたかどうかが分かります。
(4)債権者からの請求がないか注意する
借入先からの請求は相続開始後に届く場合もあります。相続手続きが進行中に請求が来た場合は、時効が停止する可能性があるため注意が必要です。
2.借金がある場合の対処法
故人に借金がある場合、相続人は以下の3つの方法から選択できます。
1.単純承認:すべての財産と借金を引き継ぐ
単純承認とは、故人のプラスの財産とマイナスの財産をすべて相続する方法です。
メリット
-
手続きが簡単で、特別な申請は不要
-
財産と借金の両方を引き継げる
デメリット
-
借金が多い場合は相続人が負担を抱える
-
相続放棄や限定承認の熟慮期間(3か月)を過ぎると自動的に単純承認と見なされる
注意点 相続財産に対して処分行為を行うと単純承認とみなされる場合があります。たとえば、不動産を売却したり、預金を引き出したりすると自動的に単純承認となるため注意が必要です。
2.限定承認:プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ
限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ方法です。
たとえば、故人の財産が1,000万円、借金が1,200万円だった場合、1,000万円までの返済義務しか負いません。
メリット
-
財産以上の借金は支払う必要がない
-
プラスの財産が残る場合は相続できる
デメリット
-
相続人全員で手続きしなければならない
-
手続きが煩雑で、家庭裁判所への申立てが必要
-
申立てには相続開始から3か月以内という期限がある
注意点 限定承認は相続人全員が同意しなければ手続きができないため、事前に話し合いが必要です。
3.相続放棄:借金を引き継がずに放棄する
相続放棄は、プラス・マイナスを含めすべての財産を放棄する方法です。
メリット
-
借金の返済義務がなくなる
-
将来の債務請求も免れる
デメリット
-
財産もすべて放棄するため、プラスの財産も引き継げない
-
相続放棄した後は撤回できない
-
相続順位が次の相続人に移る(兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合がある)
注意点 相続放棄は家庭裁判所に申請が必要で、相続開始から3か月以内に行わなければなりません。
3.どの対処法を選ぶべきか?
借金の金額や財産状況によって最適な対処法は異なります。
-
プラスの財産が多い場合 → 単純承認
-
財産より借金が多い場合 → 相続放棄
-
財産と借金が同程度の場合 → 限定承認
故人の借金は、相続人が知らないうちに連帯保証人になっていたケースや、債権回収業者からの突然の請求などで後から発覚することもあります。早めに調査を行い、状況に応じた手続きを選択することが大切です。
まとめ
相続時には故人に借金があるかどうかを必ず確認しましょう。調べ方としては郵便物・信用情報機関・登記簿謄本の確認が有効です。借金がある場合は、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択し、適切に対処しましょう。