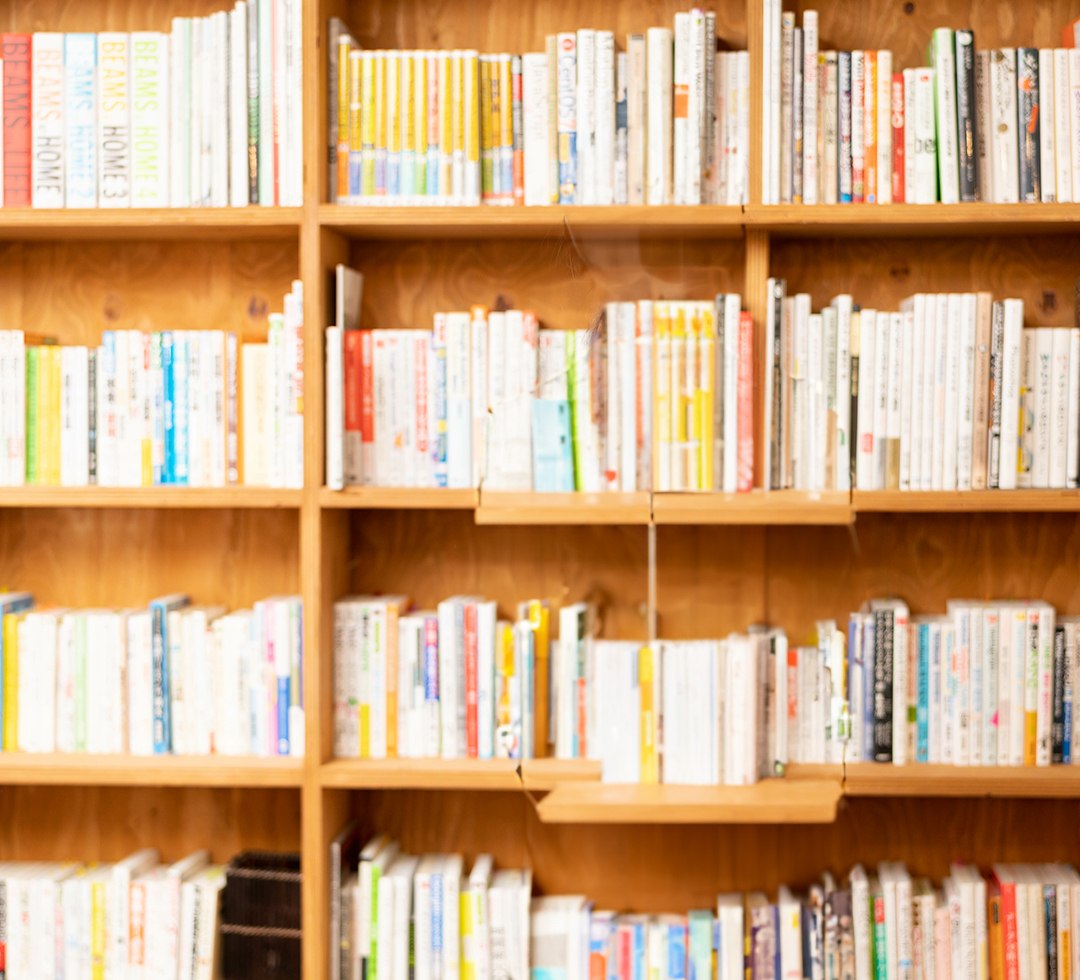オフィシャルブログ
認知症と相続の落とし穴
遺言無効のリスクと対策法を解説

日本では高齢化の進行により、認知症患者の増加が深刻化しています。厚生労働省によると、65歳以上の約7人に1人が認知症を発症しているとされています。
相続において、被相続人(亡くなる人)が認知症だった場合、遺言書が無効になる可能性があります。さらに、認知症により財産管理が難しくなると、不適切な契約や財産流出といったトラブルも発生しやすくなります。
この記事では、
-
認知症による遺言書の無効リスク
-
成年後見制度と家族信託による対策
について詳しく解説します。
1.認知症で遺言書が無効になるケースとは?
遺言書は被相続人が自らの意思で作成する法的文書です。そのため、作成時に判断能力が不十分だと無効になる恐れがあります。
遺言書が無効になるケースとは…
-
認知症発症後に遺言書が作成され、判断能力が無かったと認定される場合
-
遺言書作成時に意思能力が欠如していたと認定される場合
無効と判断されるポイント
-
作成時の診断書やカルテ:認知症が進行していた場合は無効とされる可能性が高い
-
言動の一貫性:遺言内容と普段の発言や行動が著しく異なる場合
-
医師の立ち会いの有無:公正証書遺言で医師の立ち会いがない場合は無効リスクが高まる
2.認知症対策の法的制度
認知症による相続トラブルを防ぐためには、成年後見制度や家族信託といった法的制度を活用することが有効です。
1.成年後見制度とは?
成年後見制度は、判断能力が不十分な人(認知症患者など)の財産管理や契約を代理人がサポートする制度です。
(1)成年後見制度の種類
-
法定後見制度:すでに判断能力が低下した場合に適用
-
任意後見制度:判断能力があるうちに契約を締結し、将来に備える
(2)成年後見制度の手続き方法
-
必要書類の準備
-
成年後見申立書
-
本人の診断書(医師作成)
-
財産目録や収支状況の資料
-
家庭裁判所への申立て
-
本人または親族が管轄の家庭裁判所に申立て
-
申立費用は約1~2万円
-
成年後見人の選任
-
家庭裁判所が後見人を選任
-
専門家(司法書士や弁護士)が選ばれるケースが多い
-
成年後見の開始
-
後見人が本人の財産管理や法的手続きを代行
-
後見開始後は、家庭裁判所への定期報告義務が発生
(3)成年後見制度のメリット・デメリット
メリット
-
認知症になっても財産が適切に管理される
-
不正な契約や財産流出を防止できる
デメリット
-
家庭裁判所の監督下に置かれ自由度が低い
-
後見人報酬(年額数万円~数十万円)が発生
2.家族信託とは?
家族信託は、本人が元気なうちに財産管理を信頼できる家族に託す制度です。
信託契約により、認知症発症後でも財産管理や相続対策を柔軟に行えるのが特徴です。
(1)家族信託の手続き方法
-
信託契約書の作成
-
委託者(財産を託す人):本人
-
受託者(管理する人):子や家族など
-
受益者(利益を受ける人):本人または家族
-
公証役場での公正証書作成
-
家族信託契約は公正証書にすることで信頼性が高まる
-
費用は約5~10万円
-
信託口座の開設と財産の移管
-
不動産の場合:信託登記が必要(登録免許税が発生)
-
金融資産の場合:信託専用口座を開設
-
管理と運用
-
受託者が信託財産を管理し、必要に応じて運用や売却を実施
(2)家族信託のメリット・デメリット
メリット
-
認知症発症後も柔軟に財産管理ができる
-
成年後見制度と異なり自由度が高い
-
相続発生後の承継先を指定できる
デメリット
-
契約時に費用(数十万円)がかかる
-
信託財産は受託者の管理下に置かれるため、信頼できる人が必要
3.認知症対策に必要な準備とポイント
(1)早めの遺言書作成が重要 認知症を発症する前に遺言書を作成することが最善の対策です。
-
自筆証書遺言よりも公正証書遺言がおすすめ
-
医師の診断書を添付すると有効性が証明されやすい
(2)家族で事前に話し合いを行う
-
認知症発症後の財産管理について家族と意思共有しておく
-
成年後見制度や家族信託の活用を検討
(3)専門家への相談を検討
認知症による相続トラブルは法的に複雑なケースが多いため、司法書士や弁護士と連携することが重要です。
まとめ
認知症と相続は深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。
-
遺言書は認知症発症後に作成すると無効になる恐れがあるため、早めに作成する
-
成年後見制度と家族信託を活用し、財産管理と相続対策を万全に行う
将来の相続トラブルを防ぐために、事前に家族で対策を話し合い、早めの準備を進めましょう。