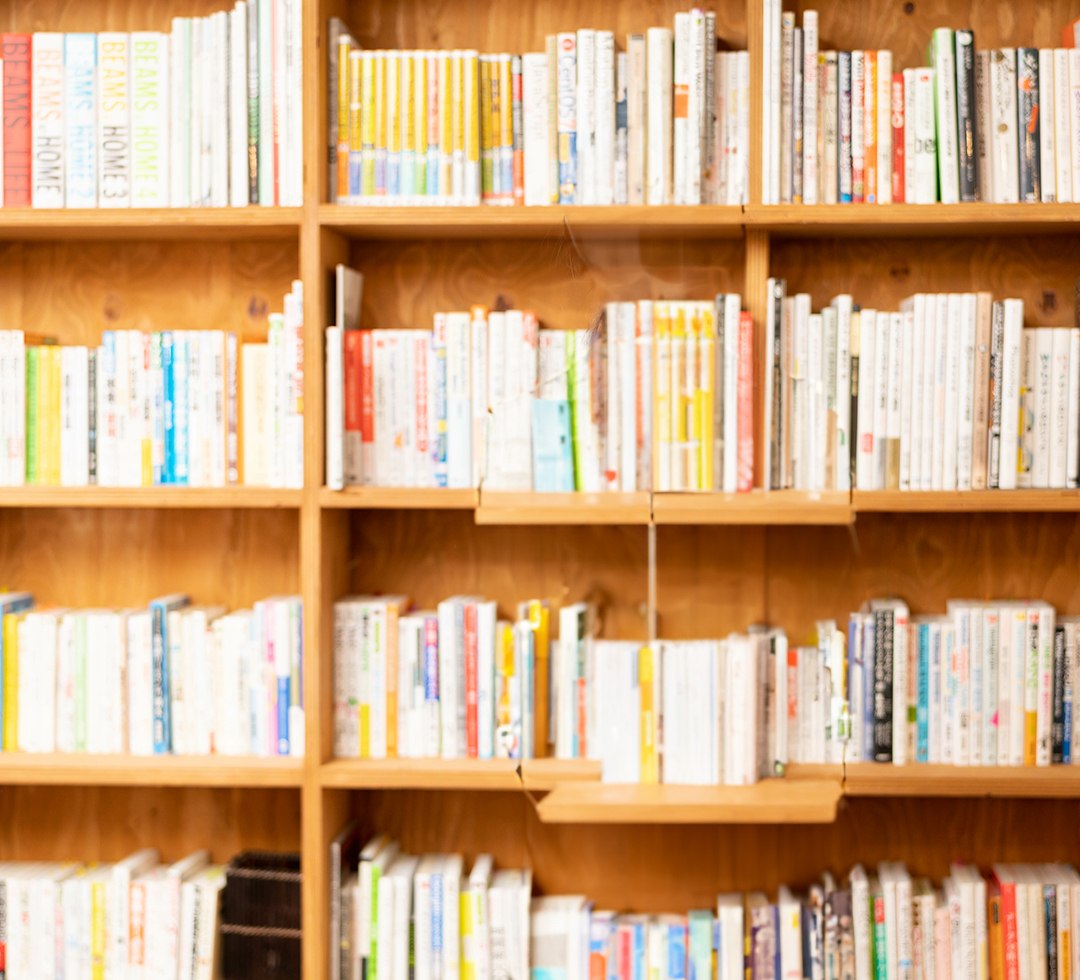オフィシャルブログ
相続税の不動産評価額はこう下げる!
具体的な計算方法と節税対策

相続税の計算では、不動産は現金や預貯金と異なり、時価ではなく評価額で計算されます。この評価額は税法上の計算方法によって算出されるため、工夫次第で節税効果を高めることが可能です。本記事では、不動産の相続税評価の仕組みと、評価額を引き下げる節税対策を詳しく解説します。
1. 相続税計算における不動産の評価方法
相続税で不動産を計算する際は、土地と建物で異なる評価方法が用いられます。
【土地の評価方法】
土地は主に以下の2つの方法で評価されます。
- ① 路線価方式
→ 市街地などで採用される方法で、国税庁が公表する「路線価」に土地の面積を掛けて計算します。
計算式:
土地評価額=路線価 × 面積(㎡)
例:路線価が20万円/㎡で100㎡の土地の場合
→ 20万円 × 100㎡ = 2,000万円
- ② 固定資産税評価額方式(倍率方式)
→ 路線価が設定されていない地域で採用されます。
計算式:
土地評価額=固定資産税評価額 × 評価倍率
例:固定資産税評価額が1,000万円で倍率が1.1倍の場合
→ 1,000万円 × 1.1=1,100万円
【建物の評価方法】
建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。
例:固定資産税評価額が1,500万円の場合 → 相続税評価額も1,500万円
ポイント:
建物は時価と固定資産税評価額に差が出やすく、時価の7割程度が目安となるため、現金よりも相続税評価が低く抑えられる傾向があります。
2. 不動産評価額を引き下げる節税対策
不動産は評価額の算出方法によって節税対策が可能です。以下で代表的な方法を紹介します。
【① 小規模宅地等の特例を適用する】
相続人が自宅や事業用に使用していた土地を相続する場合、最大80%評価額が減額される特例です。
- 自宅の場合:
→ 被相続人と同居していた親族が相続する場合、330㎡まで80%減額 - 事業用の場合:
→ 被相続人が事業に使用していた土地は400㎡まで80%減額
例:
土地の評価額が5,000万円の場合
→ 小規模宅地等の特例適用後は評価額1,000万円(5,000万円 × 20%)
節税効果:
土地評価額が大幅に引き下げられ、相続税を大幅に抑えることができます。
【② 借地権や貸家建付地で評価を下げる】
土地や建物を賃貸に出すと評価額が下がります。
-
借地権の評価
借地権付きの土地は、土地の評価額から「借地権割合分」が差し引かれます。
→ 地主が所有する土地は評価額が30~60%減額される場合があります。 -
貸家建付地の評価
建物を賃貸に出すと「貸家建付地」として評価され、評価額が下がります。
計算式:
貸家建付地評価額=自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合)
例:自用地評価額が1億円、借地権割合50%、借家権割合30%の場合
→ 1億円 ×(1 − 0.5 × 0.3)=8,500万円
【③ 建物を建築して土地評価を引き下げる】
更地よりも建物が建っている土地の方が評価額が下がります。
理由は、更地は土地全体が評価対象となるのに対し、建物がある場合は貸家建付地の評価減が適用されるからです。
例:
土地の評価額が5,000万円の場合
→ 建物を賃貸にすると、貸家建付地評価で評価額が約30%減額されるケースもあります。
【④ 広大地評価を活用する】
一定の広さがある土地は「広大地評価」により評価額を引き下げることが可能です。
適用条件:
- 市街化区域などにある
- 500㎡以上の広さ
- 一般的に分譲開発が想定される土地
計算式:
広大地評価額=自用地評価額 ×(1 − 広大地補正率)
広大地補正率は土地の規模に応じて決まります。
3. 不動産評価に関する注意点
① 不動産評価は専門家に依頼する
土地の評価は複雑なため、税理士や不動産鑑定士に依頼することで適切に評価を行えます。
② 過度な評価引き下げは否認リスクあり
評価額を意図的に下げるための過度な対策は、税務署による否認リスクがあるため注意が必要です。
4. まとめ
不動産は相続税計算において現金よりも評価額が低くなる傾向があり、節税対策に有効です。特例や貸家建付地評価、広大地評価などを適切に活用することで評価額を引き下げられます。相続対策を行う際は、税理士や不動産鑑定士と連携しながら進めることが重要です。